軽井沢ツーリング。ペンションシルバーストン宿泊。
かなりバイク趣味に振った内容で失礼します。とても思い入れのあるペンションへ3年ぶりに泊まりに行ったものでして、懐かしさ余って文章過多になるかとは思いますが、どうかご容赦ください。帰ってきてから知ったのですが、風景の写真なんてぜんぜん無かったです。まだ紅葉くすぶる群馬の山林、避暑限定ではなくなった軽井沢の交通量、谷を挟んで山並みを見渡す小諸の風景など、写真でお伝えできなくて実に惜しいです。
下の写真はバイクの防寒装備のひとつであるハンドルカバーです。ゴールドウィンという信頼できるメーカーの高いやつを持ってたのですが、以前紅葉巡りで一緒に走った友人に貸しっぱなしで、これはずっと前に買った安物を掘り出して洗濯して取り付けたものです。気温5度以上なら無難に寒さを防いでくれます。












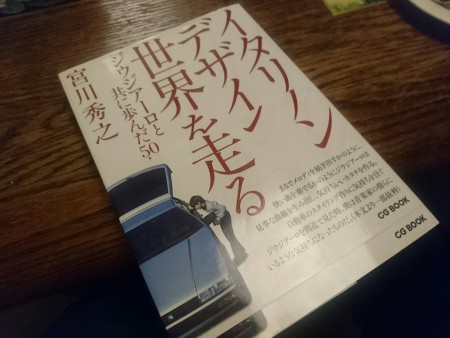
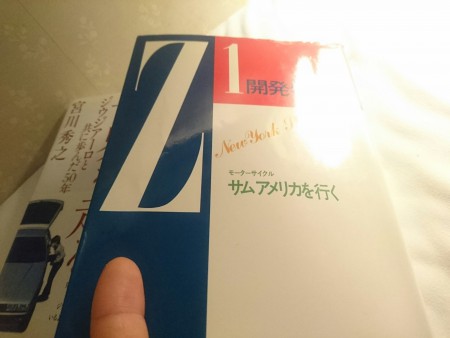




























































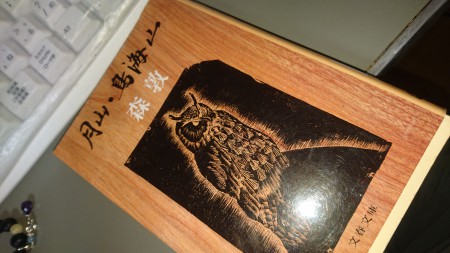
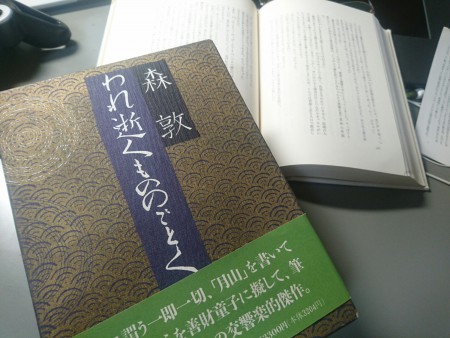


















































 稲刈りと同時並行で蕎麦刈りも別動隊によって進めました。写真はキャタピラのゆるみを修正するのに不足していた工具類を届けた時の様子です。
稲刈りと同時並行で蕎麦刈りも別動隊によって進めました。写真はキャタピラのゆるみを修正するのに不足していた工具類を届けた時の様子です。
 蕎麦刈り班の造園がうちの敷地に乗り入れたファーガソン。この風格ほれぼれします。
蕎麦刈り班の造園がうちの敷地に乗り入れたファーガソン。この風格ほれぼれします。
 若宮ばくさく珠玉の特栽コシヒカリ。休憩時間にみんなで新米を試食しました。
若宮ばくさく珠玉の特栽コシヒカリ。休憩時間にみんなで新米を試食しました。



















































 キッチントヨボ。久しぶりに来たのでナポリタンと焼きカレー。
キッチントヨボ。久しぶりに来たのでナポリタンと焼きカレー。








 キャブレターは純正で強制開閉。
キャブレターは純正で強制開閉。 スイングアームの注意書き。
スイングアームの注意書き。








 稲刈りは延々と続きます。
稲刈りは延々と続きます。











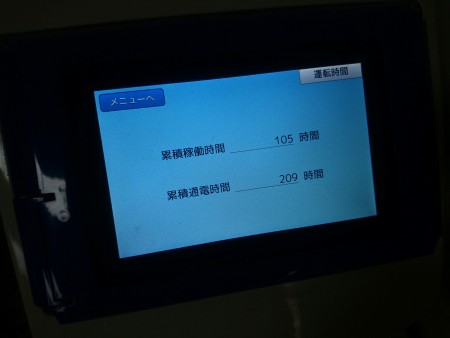 あと半分がんばります。
あと半分がんばります。